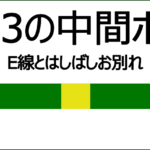明日のためのレッスンノート(vol.17)
こんにちは!コントラバス奏者の井口信之輔です。
吹奏楽におけるコントラバスへの理解と発展を願って毎週更新している『明日のためのレッスンノート』
昨年の10月から毎週更新を続けてきて、今回で第15回目となりました。
今週も、引き続きコントラバスの運指表に基づいた12のポジションを解説していきます。
前回のレッスンノートで解説した第2と第3の中間ポジションはマスターできましたか?
明日のためのレッスンノートでは、毎週ポジションを1つずつクリアしていくことを目標とし、全部で12のポジションをマスターしていきます。
今週は、また音の階段をひとつ登って新しいポジションへと進みます。
ポジションを順に覚え、知識として頭に入れ、練習を重ねて身につけ、より良いバスを弾けるようになってくださいね。
それでは!今日よりもちょっと良い明日に向けて、レッスンノートを開いていきましょう!
コントラバスの12のポジション〜第3ポジションとは?
コントラバスの運指表に基づいた12のポジション。
今回マスターするポジションは第3の中間ポジション
と呼ばれています。
まずは、第3ポジションの音列を覚えていきましょう。
- G線(ソ)…→ド(シ♯)→レ♭(ド♯)→レ(ドx)
- D線(レ)…ソ(ファx)→ラ♭(ソ♯)→ラ(ソx)
- A線(ラ)…レ(ドx)→ミ♭(レ♯)→ファ♭(ミ)
- E線(ミ)…ラ(ソx)→シ♭(ラ♯)→シ(ラx)
※ xはダブルシャープとしています。
第3ポジションまた登場!1本隣の「高い弦の開放弦と同じ音」
第2ポジション、第2と第3の中間ポジションで出てきた開放弦と同じ音がここでも登場し、第3ポジションの1の指(人差し指)で押さえる音はG線を除き一本となりの開放弦(高い弦)と同じ音になります。
- D線の第3ポジションの1で押さえる音=ソ(G線の開放弦と同じ音)
- A線の第3ポジションの1で押さえる音=レ(D線の開放弦と同じ音)
- E線の第3ポジションの1で押さえる音=ラ(A線の開放弦と同じ音)
もう一つ覚えよう!1本隣の「低い弦の開放弦と同じ音」
第3ポジションの1(人差し指)で押さえる音は、1本隣の高い弦の開放弦と同じ音であることがわかりましたね。
ここまで覚えたらもう一つ。
第3ポジションの4(小指)で押さえる音は、1本隣の低い弦の開放弦と同じ音であることを知っておくと良いでしょう。
- G線の第3ポジションの4で押さえる音=レ(D線の開放弦と同じ音)
- D線の第3ポジションの4で押さえる音=ラ(A線の開放弦と同じ音)
- A線の第3ポジションの4で押さえる音=ミ(E線の開放弦と同じ音)
第3ポジションの4で押さえる音は各開放弦よりも1オクターヴ高い音になります。
ポジションを覚える流れはこれまでと同じ!
すべての基礎となるハーフポジションからはじまったポジションの解説も少しずつ進んできましたね。
ポジションの覚え方はこれまでと同じで、各弦での音の並びを確実に覚えていってください。
そして、全長スケールの楽譜を使ってあなたが弾けるポジションのスケールを見つけて積極的に取り組んでいってください。
おわりに
『明日のためのレッスンノート』今週は、コントラバスの運指表に基づいた12のポジションより「第3ポジション」の解説をしてきました。
今回で第3ポジションまで進んだので、次回は新しいチューニング方法を紹介します。
経験者の人は、すでに知っているかもしれませんが、初心者の人は必ず覚えておきたい方法です。
このチューニング方法を身につけるには、第3ポジションで左手の形がしっかりと作れることが絶対条件です。
実際にオーケストラや吹奏楽の練習で大いに役に立つチューニング方法なので、ぜひ覚えていきましょう。
次回『明日のためのレッスンノート』は一息ついて「耳を育てよう!ワンランク上のチューニング方法」と題し、新しいチューニングのやり方を解説していきます。
チューナーに頼りすぎず、自分の耳を使って音を合わせていくことを少しずつ覚えていきましょう。
耳を育てること、これは音楽をやる上でとても大切なことです。
それでは、また来週のレッスンノートでお会いしましょう!