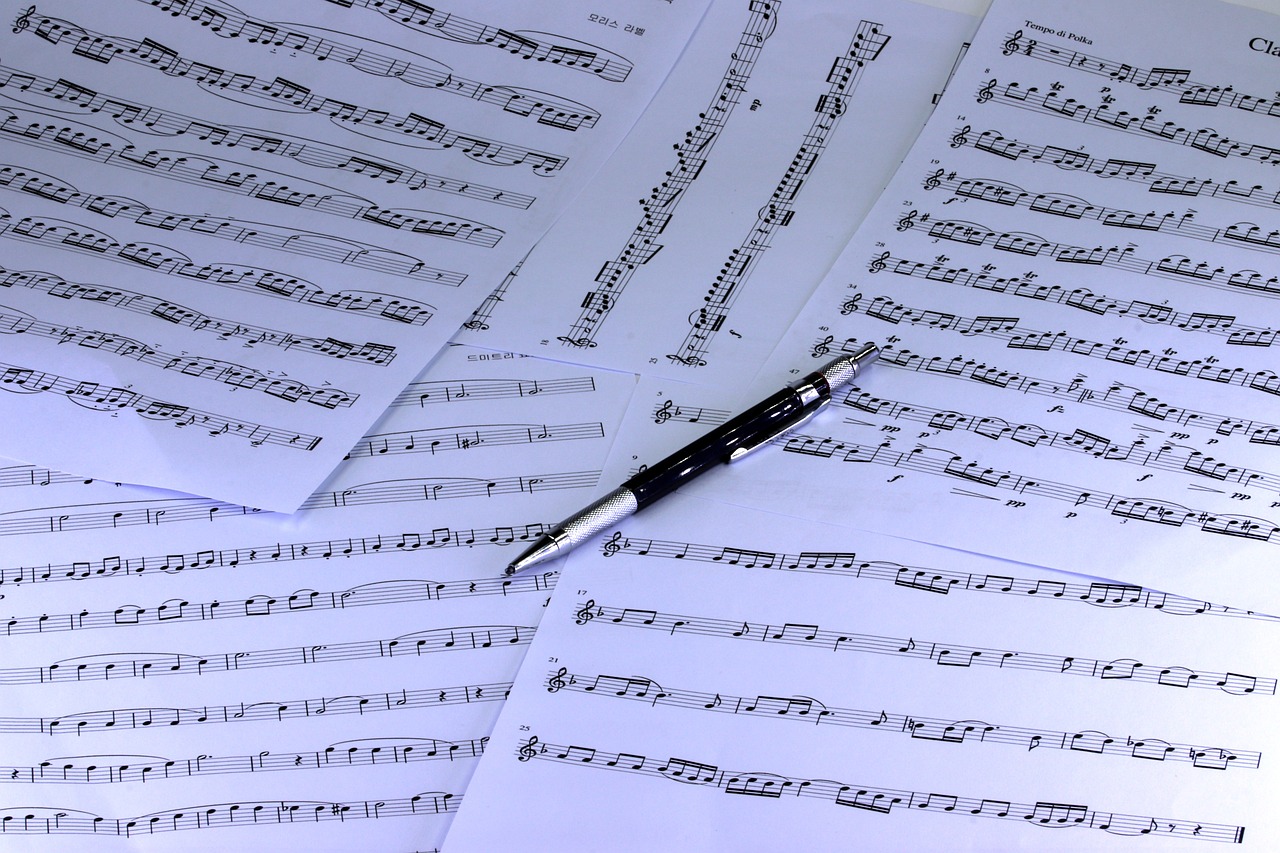コントラバス奏者、吹奏楽指導者、指揮者の井口信之輔です。
コントラバスを弾いたり教えたり、昨年度は趣味で演奏活動をしている方から音楽高校、大学受験生までのレッスンをしたり、年間を通して40校を超える吹奏楽部やオーケストラ部、大学サークルなどで音楽指導をしたり、茨城県にある取手聖徳女子高校の音楽科でコントラバスの講師を務めたりしています。
最近、「合奏指導ってどうやって勉強しましたか?」って質問を受け、そういえばどうやって勉強したかなと振り返ることがあったので、自分がどんなことをしてきたかを書いてみようと思います。
こうやれば良い指導ができる!のようなノウハウを持っているわけでもなく、僕自身もまだまだ勉強中ですが、振り返ってみてやってよかった!と感じたものを書いてみます。
合奏指導ってどうやって勉強しましたか?って質問があったので答えてみると
・演奏現場の指揮者から盗む
・合わせで積極的に発言してみる
→自分の発言で起きた変化をチェック
・自分の合奏を録音して聴き直す
→良し悪し全て紙に書き出す自分のレッスンの様子を録音して聴くが一番効果ありました。
— 井口信之輔|コントラバス𝕏吹奏楽指導 (@igu_shin) April 9, 2024
合奏の指導法は独学
僕の場合、合奏指導は独学で身につけていきました。
というか、身につけている最中と言った方が良いかもしれません。
演奏や指導で「いいね!」と思ったことを自分に取り入れるということを繰り返していました。
そして、自分の置かれた場所をうまく活用して自分自身の指導法を試してみるという感じ。
ざっくり書くとこんな感じですが、もう少し具体的に書いてみます。
演奏の現場で指揮者から盗む
技術を盗むって言い方は最近あまり耳にしなくなったように感じますが、コントラバス奏者として参加している演奏の仕事のリハーサルでの指揮者の振り方、リハーサルの進め方、また各セクションへのアドバイスなどから「いいね!」と感じたものをスマホのメモ機能とかを使ってメモしておく。
振り方であれば、帰りにトイレに寄ったときでも鏡の前で少し指揮者の真似してみるとか記憶が上書き保存される前に「こんな感じだったよな」って感覚を持ち帰るということをしていました。
たまに人が入って来ますので、他人の目が気になる場合は個室でやってみてください。
ただし、腕をドアに強打することもあるので気をつけてください。
僕はフェルマータやリタルダンドの振り方が苦手なので、ずいぶんと色々な現場での指揮者の方々から学ばせていただいました。
前はネタ帳というものを用意して、直感でビビッときた言い回しをメモしていました。
合わせで積極的に発言してみる
合わせやリハーサルのとき、自分だったこうするとか今のこの部分は何をすれば良くなるか?みたいなことを考えながら演奏しつつ、発言した方が良い流れになりそうだと思うタイミングで発言していくということをやっていました。
そして、自分の発言でどんな変化が起きたかをチェックしていきます。
良くなるときもあれば、うまく伝えられず何も変わらなかったなんてこともあります。
でも、合わせやリハーサルは自分の指導法を試してみる良い機会です。
ここで気をつけないといけないのは、自分の好みであったり「こうあって欲しい」という自分を押し付けないことで、そのリハーサルが良い方向に流れる提案をするような感じです。
指揮者を置かないアンサンブルで
例えば、指揮者を置かない弦楽オーケストラで何度かやってみて合わなかった部分があるとします。
そのときに、「きっとこの部分を調整したら合うな」と感じることがあれば、思い切って発言してみます。ただし、言葉選びには要注意で強い言葉や攻撃的な言い方はNG。
「今、休符だったので聴いてたのですが24小節目に入る付点の音形が持つ推進力からテンポをキャッチすることで上手くハマると思います」みたいな感じで、相手が考える余白があると良いかなと感じます。
アマチュアオーケストラでの発言はご法度?
これまで、アマチュアオーケストラや吹奏楽団にエキストラに行ったときは口出しするのはNGとおそわり、また耳にして僕の確かにそうだと考えています。
特にボウイングであったり、プルトを組んでいる人と譜面台を一人で使っている人がいたり、譜めくりのタイミングがバラバラだったりというときに、プロの奏者(エキストラ)が物事を点で見てしまい何かを指摘することでパートが混乱してしまうということは過去にもありました。
また、団員さんから「私は初心者なので一番後ろで弾きたい」と希望があり、指揮者にも確認をしてエキストラの音大生が前に出て団員さんが一番後ろで弾いていたとき、後から来たエキストラのおじさんが「なんでエキストラが前で弾いてるんだ、団員さんが後ろなのはおかしい!」と言って本番前にパートが混乱したというようなこともありました。
他団体に参加して演奏するときは、基本的に何も言わず音でサポートをするのが理想ですが、メンバーとのコミュニケーションをとっていく中でこれは自分の経験が活かせると感じたときは、勇気を持って発言してみると、喜んでいただけたりします。
ただし、必ず物事を点ではなく線で捉えることを忘れずに。
何かを指摘したら「先程はありがとうございました」など一言添えておくと良し。
過去に、エキストラで参加したアマチュア楽団のリハ中のコミュニケーションからトレーナーの依頼をいただいた(売り込み、営業は一切なし)ことなどあったので、実体験として書いています。
ダメ出しや指摘だけになりそうであれば黙る、相手にとってメリットを提供できそうであれば喋る。
自分の合奏を録音して聴きなおす
一番効果があったのは自分の合奏を録音して聴くことでした。
他人のレッスンを見学したり、聴講するのが勉強になるように自分自身のレッスンを聴きなおすこともとても勉強になります。
普段は気がつかない喋り方の癖、スピード、言い回しなど改めて聴くことで自分の良し悪しがわかるので、自分の合奏を録音して聴くというのが一番おすすめです。
僕の場合は、早口になりやすかったり、つい喋りすぎてしまうのが課題。
合奏を録音し、帰ってスコアをメモ帳と付箋を用意して聴き直します。
そのときに、次回の練習で合わせたいところやうまくいったところ、改善が必要な場所などをノートに手書きで書き出していきます。
自分の癖に気づいたら書き、気になれば巻き戻して聴き直し、3時間の合奏であれば4〜5時間ほどかかりますが、自分自身へのフィードバックという感じで合奏を録音しては聴き直して書くという作業をひたすら繰り返していました。
その効果を感じたのが、周りから合奏を喜んでもらえることが増えたという体験でした。
おわりに
合奏指導は勉強する場所がない。
音大を出た頃はそう思っていましたが、勉強をする場所がなければ自分で作れば良いということで、自分の置かれている環境を上手く活用していくという視点を持てるようになりました。
僕のまだまだ勉強中ですが、合奏指導ができるようになりたいとか、吹奏楽指導の仕事をしていきたいって人の活動のヒントになれば嬉しいです。
それでは、お互い頑張っていきましょう!